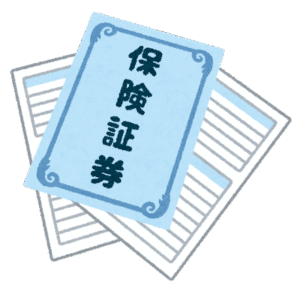源泉所得税の基本とQ&A
こんにちは! 税理士法人IUManagementです。
前回のブログでは源泉所得税の納期の特例についてお知らせしました。
7/10㈭が納付期限でしたが、皆様納付は無事終わられましたでしょうか?
事業をされていれば「源泉所得税についてまったく知らない」ということは無いと思いますが、意外と判断に迷ったり見落としてしまったりといったケースが隠れています。
今回は、改めて源泉所得税の基本的な知識をお伝えした後、判断に迷うようなケースについてQ&A形式で取り上げることにします。
<源泉所得税の基本>
国税庁が作成している「令和7年版源泉徴収のあらまし」という冊子があります。
この冒頭に源泉徴収制度について次のように書かれています。
「所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払いの際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。」
つまり、
●事業者が
●特定の所得を支払う場合
●その所得に対する所得税を徴収し
●国に納付する
という制度です。
ちなみに、この源泉徴収制度はわが国では古くは明治32年から採用されているという長い歴史を有しています。
この源泉徴収制度において、源泉所得税を徴収し国に納付する者のことを「源泉徴収義務者」といいます。「義務者」ですから、源泉徴収制度は選択制度ではなく必ず果たさなければならない「義務」として位置づけられていることがわかります。
又、源泉徴収制度の対象となる特定の所得は法律で限定列挙されており、支払相手別に規定されています。この支払相手には「非居住者及び外国法人」も規定されています。つまり源泉徴収制度の対象は日本の居住者に対するものだけではありません。このあたりは知らないと漏れてしまう落とし穴の一つです。
そういった「落とし穴」も含め、弊社でに実際にご質問があったものを中心にQ&A形式で取り上げます。
<Q&A>
Q1 源泉所得税を納付しすぎてしまった時の手続き
給与から預かった源泉所得税264,700円を納付する際、誤って納付書に294,700円と記載・納付してしまいました。どうしたらいいでしょうか?
A 税務署に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出することで納付しすぎた金額の還付を受けられます。 誤納付した際の納付書のコピーなど一定の書類の添付が必要になりますので、日ごろから書類の保存、管理にご注意ください。
又、納付しすぎた源泉所得税が給与所得に対するものであれば、届出することにより納付しすぎた税額を今後の納付額に充当することも可能です。
Q2 海外の人に賃料を支払う時の源泉徴収
本社事務所として借りている不動産の管理会社から「物件の貸主が変更になり非居住者の方になりました。今後の賃料の支払いについては借主様に源泉徴収をしていただくことになります」という文書が届きました。これはいったいどういうことでしょうか?
A 非居住者や外国法人から日本国内にある不動産を借り、賃料を支払う場合は、その支払いの際に20.42%の源泉所得税を徴収し、国に納付しなければなりません。
昔はあまりこういったケースはありませんでしたが、最近は外国人が日本の不動産を所有することも珍しいことではなくなってきました。 管理会社が間に入っている場合は通知してくれることもありますが、オーナーが非居住者や外国法人に変わっていた場合はご注意ください。
※ 租税条約の定めるところにより、源泉徴収が免除または軽減されることがあります。所定の届出書や還付請求書を国内源泉所得の支払者(賃借人)を経由して、その支払者の所轄税務署長に提出する必要があります。
Q3 セミナー講師に支払った交通費の取り扱い
セミナーをしていただいた講師に報酬を支払います。その際交通費も報酬と一緒に支払いますが、源泉徴収の計算対象は報酬部分のみでよいでしょうか?
A 交通費の名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の計算対象になります。
講師が遠方からお越しになる場合、交通費を報酬と一緒に支払うケースがあります。お車代として現金を渡すこともあり得ますが、名目はどうあれ「実態」がどうであるかを重視します。報酬として支払う金額を単に名目上報酬と交通費に分けただけなら実態は報酬と同じなので交通費も源泉徴収の対象になります。
講師を通さずに直接交通機関やホテルに支払えば報酬とは別であることが明確なので、源泉徴収の対象にはなりません。
Q4 納期の特例に該当しなくなったとき
納期の特例を適用していましたが、新入社員を迎えたことにより従業員数が10名を超え要件に該当しなくなりました。どのように手続きすれば良いでしょうか?
A 納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書を速やかに税務署に提出します。提出した月の翌月から毎月納付となり、提出した月までに源泉徴収した税額は翌月10日までに納付します。
例:3月に届出書を提出した場合は、1月から3月に源泉徴収した税額を4月10日までに納付。4月に源泉徴収した税額からは翌月10日までに納付していくことになります。
前回のブログでもお知らせした「納期の特例」ですが、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の場合に限られています。常時10人未満とは「平常の常態において」10人未満かどうかにより判断されます。
たとえば建設業のように労働者を日々雇い入れることを常態とする場合には、正社員の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる日雇いの方を含めて常時10人未満でなければ、納期の特例は適用できません。
税務調査で納期の特例が適用できないことを指摘された場合、延滞税などのペナルティを受ける可能性もありますので、要件に該当しなくなった場合には自主的かつ速やかに届出を提出し、毎月の納付に切り替えることが重要です。
<最後に>
今回はよくいただくご質問の中から4つを抜粋してQ&Aとして紹介させていただきました。
源泉所得税は日々の経理実務によく登場するため「知っているつもり」になりがちですが、実務ではもっと様々なケースが出てきます。又、支払った相手先が存在しているため処理を間違えると相手先にも影響することがあります。
ご不明な点や判断に迷うようなことがございましたらお気軽にご相談ください。