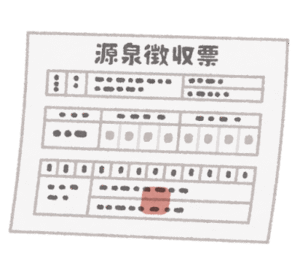住んでいる自治体で住民税額が違うって本当?
こんにちは!税理士法人IU Managementです!
皆さんは引っ越しをしたことはありますか?特に市町村の変更を伴う引っ越しをしたとき、自治体によって行政サービスが微妙に違う・・・といったことが意外とたくさんありますよね。
例えばゴミの日。分別の仕方からゴミを出せる曜日、頻度など、こんなに違うのかと驚くものです。
その行政サービスは住民税や固定資産税といった地方税が大きな原資となっています。今回は地方税の一つであり、皆さんにとっても身近な税金である個人住民税(以下、「住民税」といいます。)についてのお話をしようと思います。
1. 住民税とは
私たちが普段なにげなく「住民税」と呼んでいるものは、都道府県民税と市町村民税(東京23区は特別区民税)を合わせたものをいいます。
住民税は、個人の所得に応じて課税される「所得割」と、一定以上の所得がある場合に一定額が課税される「均等割」で構成されています。
2. 住民税はいくら以上の所得から課税されるの?
結論から申しますと、同一生計配偶者及び扶養親族がいない方で原則として前年の1月1日から12月31日までの合計所得金額が45万円超の場合、住民税は課税されます(※)。
少しややこしい話ですが、収入=所得ではなく、
○収入:経費などを差し引く前の金額
○所得:経費などを差し引いた後の金額
となります。例えば給与収入のみ、年金収入のみの収入の方の合計所得金額45万円は下表のとおりとなりますので、以下の金額を超える収入があると住民税が課税されます。
| 給与収入 | 年金収入 | ||
| 65歳未満 | 65歳以上 | ||
| 令和7年度住民税まで | 給与収入100万円 | 年金収入95万円 | 年金収入145万円 |
| 令和8年度住民税から | 給与収入110万円 | ||
さらに、被扶養者はいるか、ご自身が未成年者か、障害者控除を受けているか、寡婦またはひとり親に該当するかなどによって住民税非課税基準は異なります。
※自治体の級地区分によって異なります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。
3. 住んでいる自治体によって住民税額は異なるの?
いよいよ本題です。
基本的に、どこの自治体でも住民税の計算方法は同じです。このため、住民税額も住んでいる自治体によって大幅に違うということはありません。
ただし、自治体によっては以下のように、住民税に独自に上乗せ(超過課税)や減税を行っています。なお、以下の内容は令和7年10月時点での情報に基づいています。
【環境保全を目的とした超過課税】
37府県(北海道、青森県、埼玉県、東京都、千葉県、新潟県、福井県、香川県、徳島県、沖縄県を除く)では、森林の整備や水源環境の保全などを目的として超過課税を行っています。
また、都道府県以外ですと横浜市も均等割に900円上乗せされています。
【その他の超過課税の一例】
○神戸市
認知症の診断助成や事故時の救済を行う財源として均等割に400円上乗せされています。
超過課税の話ばかりしてきましたが、一方で減税している自治体もあります。
【減税の一例】
○名古屋市
均等割から200円、所得割は0.3%減税されています。
終わりに
今回は住民税についてお伝えしました。
当たり前のように給料や年金から天引きされている住民税ですが、毎年5~6月に自治体から届く通知を見てみてください。
特に都道府県を跨るお引越しをされたばかりの方は、住民税も自治体によって差があるものなのだと実感される方もいらっしゃるかもしれません。
ご不明な点やお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください!